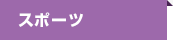大の里や草野も元王者 学生相撲の全国体重別、31日に節目の50回
東京・千代田区の靖国神社相撲場で31日に開催される全国学生相撲個人体重別選手権大会(日本学生相撲連盟主催、毎日新聞社など後援、大正製薬、伊藤園協賛)は今年、50回の節目を迎える。大相撲やアマチュア相撲で名力士を数多く輩出してきた大会の歩みを振り返った。【大村健一】
◇初代王者は角界を沸かせたあの人気者
第1回大会が開かれたのは1976年10月。会場は当時、東京・台東区にあった蔵前国技館だった。現在は8階級の大会も当初は軽量級(75キロ未満)、中量級(90キロ未満)、重量級(90キロ以上)の3階級だった。重量級を制したのは、近大の長岡末弘選手。後に「大ちゃん」の愛称で親しまれた元大関・朝潮(先代高砂親方)だった。
84年の第9回から70キロ未満~無差別級までの6階級となり、同年の無差別級はアマチュア相撲を席巻した日大・久嶋啓太選手(元前頭・久島海)が1年生で制覇。86年から日体大の斎藤一雄選手(現監督)が無差別級で2連覇を含む3度の優勝を飾った。
無差別級では、その後も、93年の中大・出島武春選手(元大関・出島)、94、95年の拓大・後藤泰一選手(元関脇・栃乃洋)、98年の日大・加藤精彦選手(元小結・高見盛)が王者に輝き、角界でも活躍した多くの選手たちがその名を連ねている。
◇体重別ならではの軽量級力士の活躍
軽量級の選手にスポットが当たるのも、この大会ならではの魅力といえる。87年に85キロ未満級で優勝したのは日大・長尾秀平選手。「技のデパート」の異名を誇る多彩な取り口で小結まで昇進し、現在は相撲解説者やタレントとしても人気の舞の海秀平さんだ。
さらに異色なのは、2011年に最軽量級の65キロ未満級を制した関西学院大の宇良和輝選手。在学中の4年間で肉体改造し、14年にはなんと無差別級で3位に入った。大相撲に進んだ現在は、本名と同じしこ名の宇良として幕内で活躍。約140キロまで体重を増やし、居反りなど大技を駆使したアクロバティックな相撲のみならず、正統派の押し相撲も武器にしている。
軽量級からは近年も、13、14年に85キロ未満級を連覇した金沢学院大・中村友哉選手(幕下・炎鵬)や、18年の同級王者、日体大・宮城陽選手(十両・宮乃風)らが羽ばたいた。
アマチュア相撲も主要な国際大会は体重別で、この大会で結果を残した軽量級の選手たちが世界でも活躍している。
◇大相撲力士ずらり 昨年は大記録も
近年は、大学相撲出身者が関取(十両以上)の約5割を占めるほど増加しており、この大会での入賞経験を持つ力士も多い。横綱・大の里は、日体大時代の19、21年に135キロ以上級で優勝、新入幕だった7月の名古屋場所で11勝を挙げた草野も日大時代の21、22年に無差別級を連覇した。
1月の初場所で優勝決定戦に進出したカザフスタン出身の金峰山(日大出身)は20年の135キロ以上級を制し、24年春場所で110年ぶりの新入幕優勝を果たした尊富士(日大出身)は19年の135キロ未満級で準優勝。選手たちのその後の活躍ぶりは枚挙にいとまがない。
昨年は135キロ未満級で日大・花岡真生選手(幕下・花岡)が他階級でも前例がない4連覇を達成。名古屋場所は幕下で6勝1敗の好成績を挙げた。大相撲でも活躍が期待される未来のスター力士に、早くから注目できるのも大会の楽しみ方の一つだ。
-
大阪ガスが4年ぶりに2回戦進出 信越クラブ降す 都市対抗野球
第96回都市対抗野球大会は第5日の1日、東京ドームで1回戦があり、大阪市・大阪ガスが長野市・信越クラブに4―1で勝ち、第92回大会(2021年)以来、4年ぶり…スポーツ 1時間前 毎日新聞
-
予告先発は末吉VS新垣有 沖縄尚学対決に 野球U18W杯壮行試合
9月2日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催されるU18(18歳以下)高校日本代表と沖縄県高校選抜による壮行試合で1日、両チームの先発投手が発表された。高校代表…スポーツ 2時間前 毎日新聞
-
王子が2年ぶりの本大会勝利 パナソニック降す 都市対抗野球
第96回都市対抗野球大会は第5日の1日、東京ドームで1回戦があり、春日井市・王子が延長十回タイブレークの末に門真市・パナソニックに7-6で勝ち、2年ぶりの本大…スポーツ 4時間前 毎日新聞
-
ウクライナ出身の安青錦が「史上最速」新小結 大相撲秋場所番付発表
大相撲秋場所(14日初日、東京・両国国技館)の新番付が1日、発表された。7月の名古屋場所で千秋楽まで優勝を争い、技能賞に輝いたウクライナ出身の安青錦が新小結に…スポーツ 12時間前 毎日新聞
-
「彼が打つと盛り上がる」 東京ガスが見せた意地の4連打 都市対抗
◇第96回都市対抗野球大会1回戦(31日・東京ドーム) ◇〇太田市・SUBARU8―3東京都・東京ガス● 六回まで太田市にほぼ完璧に抑えられ、東京都の安…スポーツ 21時間前 毎日新聞